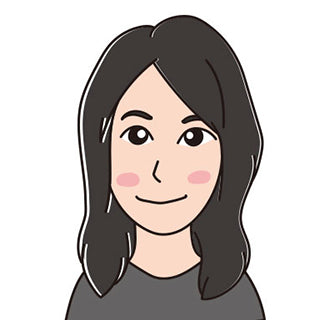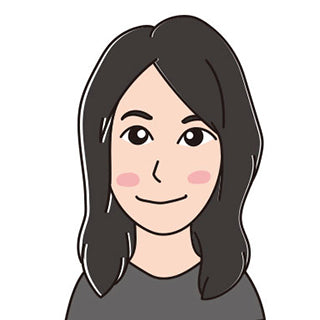日本人が誰も知らない偉大な職人シリーズ 第1回目は海外から高い評価を受け、技術指導の引く手あまたな盆栽職人 平松浩二。世界の平松と呼ばれるようになるまでの軌跡を生い立ちから追う。
国内出荷量の80%のシェアを占め、日本一の松盆栽の産地‘高松’。高松盆栽は、盆栽の競技会でも多くの賞を取り、これまでに高松からあまたの名品を輩出してきました。盆栽の聖地と言われる高松にて、ひときわ松柏盆栽の名手として知られる平松浩二さん。150年続く平松春松園の4代目で、今や、その活動は日本国内に留まらず、欧米、東欧、アジアなど、海外の展示会・講習会などに講師として赴き、活躍の場を広げています。奇をてらわず、盆栽の王道を貫きながら、世界を股にかけ精力的に活動する平松さんに今までの軌跡、これからの活動についてうかがいました。
平松浩二(ひらまつこうじ)
昭和42年12月23日生まれ
150年続く盆栽園『平松春松園(ひらまつしゅんしょうえん)』4代目園主
日本盆栽協同組合 組合員
日本小品盆栽組合 組合員
(公社)全日本小品盆栽協会 常務理事
(公社)全日本小品盆栽協会 認定講師
雅風展実行委員会 実行委員長
JA香川 国分寺盆栽部会 部会長
グリーンフェスタ国分寺実行委員会 実行委員長
香川県盆栽生産振興協議会 副会長
(公社)全日本小品盆栽協会 讃岐国風小品盆栽会 事務局
父
平松国昭(くにあき)
昭和19年8月31日生まれ
3代目『平松春松園』園主
日本盆栽協同組合員
日本小品盆栽協同組合員
日本盆栽協会公認講師
全日本小品協会認定講師
『平松春松園』の敷地面積は約2,000坪。1メートルを超える大型の盆栽から手のひらサイズの小品盆栽までを手がける全国レベルの棚場を展開し、各地の展示会や品評会にも出品。
特に注力しているのが、高松松平家第12代当主松平頼(より)寿(なが)(※詳細は盆栽の歴史ページを御覧下さい)が確立した小品盆栽。4代目園主平松浩二さんは全日本小品盆栽協会の常務理事を努め、高松市の盆栽どころでは、小品の第一人者と目されている。
年数回の海外の展示会でのデモンストレーションにも赴き、外国人の研修も積極的に受け入れている。
info
『平松春松園』
盆栽の販売・手入れ・レンタル
香川県高松市国分寺町新居2365-2
電話番号087-874-0335 携帯:090-8697-0332
HP http://syunsyouen.com/
国際感覚への媒介は盆栽
「明日からオーストラリアで講習会があって3週間ほど不在になる」
聞けば、取材に訪れた次の日から、招聘され、シドニー郊外ローズヒルで、平松さんの得意とする‘小品盆栽’のオープンフォーラムがあるという。デモンストレーション、技術講習、プレゼンテーション、ディスカッションなどがあり、技能はもちろんのこと、会場や用意された素材への適応力、想像力が試される場だ。
「準備は剪定や葉摘み用のはさみや、針金切など基本的な道具とパンツを入れるだけ(笑)」
高松から車や飛行機など諸々乗り継いで、シドニー中心部から約20km離れた、ローズヒルまで単純計算で15時間強。待ち時間を入れるともっとであろうが、平松さんにとっては、海外に行くという気負いもない。
通算すると年2ヶ月近く海外でのデモンストレーションや講習会で日本を留守にする。そいう生活をもう15年近く続けている。
2011年に高松市で開催された、世界的盆栽の芸術祭『ASPAC(アジア太平洋盆栽水石大会)』には、約30カ国・地域から計76,000人が来場。これを契機に海外での講習会や展示家でのデモンストレーションなど、以前にも増して要請があり、積極的に活動するようになった。フランス、イタリア、ポーランド、カナダ、中国などあまたの国を訪れた。
これらの国では通訳もつけずに、ほとんど身1つで英語で渡り歩く。
HIRAMATSUの盆栽をぜひ学びたい、という外国人も跡を絶たず、積極的に受け入れ、サポートしている。海外デモの頻度や外国人の受け入れ頻度を鑑みると盆栽業界では稀有な存在だ。
父である3代目『平松春松園』の園主国昭さん(75)も、育てた盆栽を販売するという従来の盆栽園の主流だったところから、この辺りでは先んじて、展示会に出品するというようなことをはじめた人だ。
展示会に度々出品するうちに、国内外で国昭さんの名匠としての技も知られるところになった。国昭さんの下で、盆栽を学びたいという人がかなりの数いて、園では人の出入りも少なくなく、外国人も代わる代わるやってきていたそう。
カナダ出身のジェリーさんは、父国昭さんの代から『平松春松園』に盆栽を学びに来ている常連だ。平松さんの小さい頃からよく知っており、代替わりしても定期的に『平松春松園』を訪れている。
ジェリーさん以外にも『平松春松園』に平松さんが幼少時代から定期的に訪れている外国人も少なからずいる。『平松春松園』に1ヶ月程寝泊まりし、滞在したりもしている。
「小さい頃家の中に外人がいて、生活しているわけでしょう。肌の色、目の色なんか違うところから不思議なわけ。生活様式も違うでしょう。母親とかがいちいち説明したりしていて、まず部屋では靴を脱ぐところから教えて、子どもがやったらすごく怒られること、例えばお茶碗や味噌汁なんかを置いたままご飯を食べるとかからね。僕なんかも話しかけられたりして、‘milk’とか‘water’くらいのもんやけど、オウム返しに言って、冷蔵庫から出してあげると、‘thank you’って言われてね、なんかおもしろかったね」
はじめこそ物珍しさもあったが、年月を経ていくうちに外国人が出入りする環境にも慣れた。
子ども時代のそういった経験があったからか、大学時代は一般教養の英語を一生懸命勉強した。特にリスニングを頑張ったそうだ。
「子ども時分、外国人が何か話しかけてくるのにわからなくて、黙っている、適当に返事をする、恥ずかしくなる、みたいな経験もしたし」
“日本と違う国、日本語と違う言語、だけど日本の盆栽をわざわざ習いにきている。親父を、‘マスター’と呼んで敬意を持って教えを乞うている”、そんなことを肌で感じ、誇らしかったという。
「幼い頃から、盆栽職人さんたちの中で過ごしていて、もちろんみなさん黙々と作業をしているんだけど、その点外国人も同じでね、僕が行ったことのない国の人たちが、僕の親父と僕ん家の盆栽園を見つけて遠いとこから来ている、けど、盆栽に向き合う姿は日本人と変わらんな、と思ったよ」
子ども時代に感じた世界の人とつながるおもしろさは、平松さんの脳裏に焼き付いたようだ。技術力と英語力で、あまたの国を股にかけ、国際舞台で活躍する土台となった経験、国際感覚への媒介は盆栽が担ったことになるようだ。
1ミリの疑問もなく
「盆栽園を継ぐことに疑問を持ったことはなかった」
小学校から高校まで野球に明け暮れた毎日。
勉強をさぼったり、部活をさぼったりすると、父国昭さんから容赦なく手が出て、足が出たという。
「怒られるのも怖くてイヤだったし、それなりに小さな反抗心もあったけど、よくよく考えると自分が悪くて、理不尽な感じはしなかった」
国昭さんは、普段は口数も少なく、浩二さんが思い出す父の姿は、黙々と作業場で盆栽に鋏を入れる姿。
「なんか集中しているな、邪魔しちゃだめだな、話しかけちゃだめだな、と子ども心に感じていたかな」
父が黙然と作業している姿は、ともすれば緊張感も伴い、自分もやるべきことをやらないと、という考えに至ったそう。
「勉強でも何でも自分なりの一生懸命さでやらんといかんな」
時には寝食忘れて盆栽に向かう父の背中を見ながら、そんな考えがストンと落ちてきた瞬間があった。野球を頑張って、勉強も頑張った。
が、地元の香川大学農学部を受験するが失敗。
父の恩師にあたる人が、見つけてきてくれたのが千葉大学の園芸学部だった。
国立大学唯一の園芸学部として当時80年程の歴史と伝統があり、国際的に通用する人材育成にも力を入れているという教育方針に惹かれた。高松を、親元を離れてみたいという気持ちも大きかった。
「結局は親父のつけた道筋やったけど、積極的に乗っかったのは自分やったかな」
浪人時代の1年間、家にはいたが、盆栽について何か手伝えというようなことはまったく言われなかった。ただ、勉強をさぼっているような兆候があると猛烈に怒られた。
死にもの狂いで勉強し、晴れて合格。
大学4年間は、酒、たばこも含め一通りの享楽を覚え、適度に遊んで楽しく過ごしたが、盆栽について勉強したわけではなかった。卒業論文も盆栽とは無関係の「ラン科植物の光合成」についてだった。
「不思議やったんやけど、道筋をつけた割に盆栽について勉強しろ、とは父親からはまったく言われなかったね。こっちから盆栽についてどうとか聞くこともなかったし」
関東圏は埼玉県を筆頭に盆栽園が集中する土地柄、展示会も比較的開催されている方であるが、盆栽園も行ったことがなければ、盆栽展にも出かけたこともなかった。
盆栽とは無縁で、親元から離れて自由な学生生活を謳歌する日々。
「今思えば大学時代は父が与えてくれた猶予期間やったんやないかな」
あの頃は父も40代半ばに差し掛かり、人生の機微も少しわかってきた頃だっただろう。一旦盆栽の世界に入れば盆栽漬けの日々になるというのを父は身をもってわかっていたのではないか。
父には面と向かって言ったことはないが、園芸学部という大義名分を与えてくれ、そうやって静観していてくれたことがありがたかった。子どもの頃から長男だからという刷り込みはあったとはいえ、血気盛んな20代前半。感謝もあったからこそ、すんなりと高松に戻って、気持ちを切り替えることができた。
「まず感謝したし、4年間の自由度があったから卒業と同時に盆栽の道に、1ミリの疑問もなく、気負いなく入ることができたのかもしれないね」
もう1つ、子どもの頃からの解けない疑問……
「盆栽に真摯に向き合う父を見てきたのも大きかった……盆栽とはいったいどんなものかと」
‘見て覚えろ’、が基本

大学卒業と同時にはじまった修行の日々。
最初の10年は‘基本の10年’で、水やりから、針金かけ、芽摘み、植え替え、剪定など基本的な一通りを覚える。
小さい頃から盆栽は身近にあって、職人さんたちが見ていて何をしているかなんとなくはわかっていたつもりだったのが、繰り返される毎日の作業に、単調で1番嫌気が差したのもこの10年だ。されど、逃げることは考えなかった。
少しずつ盆栽のことがわかっていくことに、おもしろさも覚えたからだ。
盆栽では、‘水やり3年’というが、3年とは樹の状態を見極められるのに要する期間。表土が白っぽくなったら鉢の底から抜けるくらい水を与える、というのは本にも書いてある。
「葉が弱ってないか、虫が付いていないか、根腐れを起こしていないか、など1つ1つの盆栽の声を聞くというか、その声が聞こえる瞬間があって、そうなると自分の樹に対する姿勢も変わってきて、樹と対話できるようになるわけだから、水やりも俄然おもしろくなってきたりする」
大学時代の園芸学部で学んだことも、結局は樹と対話する際、礎になった。
何より、‘盆栽を仕事にするというのがどういうことか’について身をもって学んだ10年だった。
仕事場にいようがいまいが、昼夜を分かたず親方と弟子の関係。仕事場では会話することもない。樹形を整えるための針金掛けや、剪定など、盆栽についての技術面での指導や助言は一切受けたことがない。
“親父は僕から見たら立派な盆栽職人で何でもできる。そんな親父の見よう見まねで盆栽職人としての日々を送るが、近づこうと思うが近づかない”
そんな焦りが充満していた。
「1日がかりで針金を掛けて整えた樹があって、自分なりには一生懸命やったんだよね。うまく仕上がっているんじゃないか、親父も納得してくれつんじゃないかなんて思うくらい(笑)。翌朝黙って枝が切ってあって、親父はそれについては何も言わない。ものすごく精神的にきつかった、きつかったんだけどよくよく考えたら、親父のメッセージというか、‘いらない枝に何で針金を掛けたんだ’ということだと」
落ち込んだ先に見えたのは、自分で考えなければならないのは当然だが、自分で考えるヒントを親父がくれている、とプラス思考、ならば……思い切りぶつかっていこう、という気概が生まれたという。
それから、段々と自分なりの盆栽への向き合い方を確立はしていったが、父に近づいたと思っても、その日、その時でしかできないものもある。ゴールがあるわけではない。
「親父の作った盆栽と自分の作った盆栽は明らかに違っていて……。数ミリの差の違いで随分と仕上がりが違うのがわかる」
一般の人から見たらわからない僅かの差を追求していく。
自分なりの完璧な形を常に追い求めて、樹に向き合う。
「盆栽は自己満足の世界かな」
その時はできた、完璧と思っても、樹は生きとし生けるもの、刻々と形を変える。
自然の何千年、何万年という営みの中、普遍的な自然の持つ力強さとほんの一瞬の儚い美しさのバランスが相まって生まれるもの。
だからこそ、盆栽には奥行きがあり、厳かでもあり、場合によっては神聖な趣さえ漂わす。
「樹1本1本真剣勝負は当たり前。ずーっと一生懸命白球を追いかけていたから考えるのかもしれないけれど、スポーツの‘心技体’があるよね、盆栽においても‘心技体’が充実するというか、‘盆栽の心を理解し、盆栽の仕立て、手入れの技術を身に着け、仕立てられた盆栽を興がる’というようなところにも行き着くんじゃないかな」
盆栽になる樹との一期一会がある。
「せり(盆栽用の樹のオークション)なんかで、‘ピン’と来た樹っていうのがあると値段関係なく、やけくそ、意地になって買ってしまう時があって……」
そういう樹はやっぱり自分がやったらおもしろくなりそう、やったら楽しそうという樹。
せりの時は父と離れた場所にいるのが常であるが、時に気がついたら父といっしょの樹を競り合っていて、いつまでもせりのラリーが続き、仲買人さんから、“親子で競り合うのはやめなさい”、と注意されることも、多々あった。
「僕がやめとこうと引く場合も多くて……なんと言っても僕の‘マスター’なので。気がつくと親父と同じ樹を競っているということに、恐縮もするけど、うれしくもあったね」
言葉少ない父と考えていることが一緒なんだ、親子なんだって認識する瞬間でもあったからだ。
「代替わりしようが、何しようが、たとえこの世にいなくなったとしても親父は僕の‘マスター’であることは変わらない」
終わりなき盆栽の世界
苦しんで苦しんだ最初の10年。そこをようやっと超えてきて、展示会での仕事ぶりや、手入れを任されたお客さんの盆栽が賞を取るなどし、雑誌やテレビなどの取材も受け、あちこちから声がかかるようになった。
「キャリアは長くなってきているけど、僕、盆栽のセンスがないと思う」
国内外にデモや講習で飛び回り、外国人からも「マスター」と慕われる平松さんから意外な言。
「自分以外の人が仕立てた盆栽も見て楽しいというか、たまに思う、この人こういう風に針金かけるんや、樹を曲げるんや、ここを切ってしまうんや、と」
自分では思いつかないようなことをする人がいる、センスあるな、すごいなと思う。
一方で自分はセンスがなくても、盆栽が好きだ、盆栽を死ぬまで触りたいと思っている。
「外国人に‘マスター’って呼ぶのをやめてって言っているんよね、僕も一生研鑽の日々で、ある意味同じ立場でもあると思うから」
盆栽には終わりはない。
終わりはないが、盆栽に真っ向から向き合うための年齢、体力の限界はある。
「親父は絶対的に僕の親方やけど、親父の仕事も甘くなったと感じる」
例えば、高松の盆栽園には樹高1メートルを優に超える黒松が少なからずあり、もはや盆栽と呼べないような状態。
庭木にしか有用がないと思われたこういった黒松を、盆栽としての姿に戻すため、太枝を鉄棒で曲げるというような力技もある。平松さんが30代前半だった頃には、国昭さんと2人がかりで鉄棒でもって巨木を曲げ、曲げては休憩を入れ、また曲げるを繰り返す肉体的にも精神的にもハードな作業を行っていた。
最近では、それも1人の作業だ。
「盆栽の枝を曲げたり、枝の位置を変えたりするため3本の指で針金をかける。この3本の指は職人の心臓ともいうべき部分。3本の指が思うように動かなくなったり、樹を曲げる力や技術も最盛期と比べると劣ってきたりすると、盆栽職人としてのピークは過ぎた、ということ」
盆栽をもっとこうしたい、ここを少し下げればというような数ミリの違いが、盆栽の刹那的な理想形を作り出す。数ミリの差は3本の指にかかっているのだ。それが思うようにならない日がいつの日かくるという。
「運動会のかけっこなんかで、気持ちがもっともっとって思っているのに身体がついていかなくて、足が前に出ず、転んでしまうというようなことだね」
国昭さんも65歳を過ぎたあたりから、3本の指の壁にぶち当たった。
とはいっても、今でも起きたらまず居住の場としている2階から1階の作業場に降りて、明け方5時に起き、作業場の一角に鎮座し、食事や排泄などの基本的な人間の営み以外は盆栽に向かっている。
平松さんとて同じ。起きたら居住の場としている2階から1階の作業場に降り、国昭さんと同じく、明け方5時に起き夕方6時まで所用以外は指定の場所に座って盆栽に向かう。
「起きたら盆栽というのが親父も僕も当たり前というか」
1度若い時に飲んで朝帰りで、午前4時ごろに泥酔した状態で帰宅した。玄関を開けたところに作業場があるのだが、すでに国昭さんが座って盆栽を一生懸命手入れしている。平松さんが目の前を通っても、“遅いな、何してきた”などと、言わず聞かずで、黙って盆栽をいじっていた。酔いが冷めた。
無言で盆栽への向き合い方を、身体全体から語っているようだった。
いつでも親父の背中を見てきた。
今平松さん自身には大学生の息子がいるが、“家業を継ぎなさい”という話はしたことがないという。
一旦盆栽の世界に入れば、盆栽漬けの日々。盆栽は生き物、こちらが休むということができない……自分も身をもって知った、決して派手ではなく、地道な作業の連続の日々。
その上、国内の盆栽人口が減り続けているのは、盆栽業界全体が肌で感じている危惧。平松さんの所属している日本盆栽協同組合(※平松さんの話では盆栽協会だった)の組合員も、減少の一途を辿り、最盛期の3分の1程度までになってしまっている。他の盆栽関連の団体にしても同様だ。
「これから拡大していく業界という見通しも立たず、儲けようという商売でもないから、息子には言えないかなと」
ただし、平松さんが大学卒業後盆栽の道に入った当時は、国内の盆栽人口もまだそこまでは少なくはなく、業界、地域にも活気があり、状況はやや違ったようだ。
「ただ、親父なりの先見の明というか、もしかしたら、僕に家業は継いでほしいけど、業界自体の先行きの不透明さもあり、大学時代うるさく言わなかったのかもしれない、ふとそう思う時はある。親父は親父でこの辺りでは革新的なことをはじめた人だから、僕にも期待もあったんだろうけど。親父も僕ほどにないにしてもそういう気持ちが少しあったのかもな。自分が『平松春松園』の4代目、大学生の息子のいる親になって思うね」
高松から盆栽ファンを増やすために
平松春松園のある高松市国分寺には約40の盆栽園があるが、後継者問題は切実だ。
一般的にはあまりよく知られていないが、松の盆栽生産量は香川県が日本一。高松市国分寺地区から鬼無地区にかけては全国シェア8割を占める松盆栽の一大産地。国分寺地区はその半分近くを生産している。
国分寺町盆栽集出荷場のすぐ側に「盆栽神社」があり、樹木の神様と草花の神様を祀った日本で唯一の神社。まさに盆栽の聖地だと自信をもって言える。
1950年代〜1960年代の高度成長時には盆栽業も全盛期で、隣接する鬼無地区と合わせて盆栽園も300軒程も数えていた。それが今は100軒まで減少している。
現代の住宅事情では、ある程度の大きさの盆栽を置けるようなスペースを確保するのも難しく、住環境の変化や、ライフスタイルも多様化し国内では閉塞感が強くなっている。
「僕たち盆栽園の仕事は、日々の手入れをし、育てた樹、盆栽を売るということ。他にお客さんの盆栽を預かって手入れをし、飾りたい時に飾れる状態にしておくことや、展示会出品のために手入れすることなどが主。それだけでは、ビジネスモデルとして成り立たなくなってきていて、当然考えられるのは海外への販路開拓になるよね」
中国や台湾、欧米から日本の盆栽に熱い視線が送られている。2011年のASPACを契機に多くの盆栽が輸出されるようにもなり、年々国全体、香川県全体としても往々にして輸出額は拡大傾向にある。
2013年には鬼無・国分寺地区の盆栽園主を主な構成メンバーにより、高松盆栽輸出振興会を設立。日本貿易振興機構(JETRO)のサポートを受けつつ海外バイヤーを招待したり、多言語のHPよりを開設したりと、海外販路開拓に取り組んでいる。
2001年に6億4000万円だった盆栽・庭木の輸出額は、2009年に一時落ち込みを見るが、2016年には80億円を突破し、海外市場への期待は高まる。
「国内市場が縮小していて輸出を伸ばしていくというのも必須ではある。そっちは官民一体で取り組んでいるところもあるんだけど、もう1つは絶対的に日本の盆栽、高松盆栽のファンを増やしたい。海外でデモをしていると、盆栽を通して日本を好きになってくれたり、日本文化に敬意を払ってくれたりしているというのを肌で感じる。クールジャパンじゃないけど、盆栽から日本を好きになってくれるなんてすごくエキサイティングだよね」
平松さんが招聘される、盆栽のデモンストレーションや講習会も、時には武道の実演やワークショップ、折紙教室及び箸体験、着物の着付けの実演や浴衣の着付けなどの日本文化プログラムも合わせて実施し、開催国、近隣諸国から多くの盆栽ファン、日本ファンが訪れるそうだ。
海外での活動を機に、平松春松園に研修に訪れる外国人もいる。最近では一度に海外から4人の外国人を受け入れた。そうなると手狭になり、物理的にも、気持ち的にも回りきらない感もあったという。人数が増えるのもそうだが、外国人が研修に来ている間に、平松さん自身が海外でのデモンストレーションや講習があると、司令塔がいなくなり、残された家族の負担が増すのも気がかりだ。受け入れる方と来る方のお互いのストレスにもなりうる。
盆栽人口を増やすため、整った環境で自分と自分の盆栽に惹かれてやってくる人に、ストレスの少ない環境で思い切り、指導をしたい。
「おかげさまで海外に呼ばれるようになり、デモンストレーションするとか、教えるとかの機会に恵まれているのだけど、それをもう1歩すすめて、国内外から高松に人を呼びたいと思うようになった。高松盆栽を知らしめるため、拠点を持って腰を据えて活動していきたい」
以前は、海外に呼んでもらって、異国の空気を吸って、新鮮だったし、おもしろさも感じ、リフレッシュしていた部分もある。
「宿泊施設を備えた盆栽の研修施設を作る。親父の代から外国人は受け入れていたけど、体系だってやるときが来たと思っている」
海外への招聘も38歳ごろから通算してもう100回にも上り、自分なりに外国人が盆栽について何を知りたいか、どういうことを望んでいるかわかってきた。それらがデータとして蓄積してきた。結果、ここ‘高松’でやることに意義を見出した。
「整った環境の中、研修を受けてもらって、そこで教えた人の中から、後進を育成していくような人が出てきてもらえたら」
‘本物の盆栽’を守り抜き後世に伝えていく
「外国人が研修施設に集まったら、近所の小学生たちを集めて英語教室とかもできたらいいな。それでもって、盆栽のことも、子どもたちにもっと知ってもらえたらいいと思う」
母校である地元の国分寺小学校で、毎年3年生を対象に盆栽づくりを指導している。小学校の通学路には数々の盆栽園や、盆栽用の樹を育てる盆栽畑が広がっている。この地区の子どもたちにとっては当たり前かもしれないが、なかなかない光景だ。
もしかしたら、僕が今やっていること、やろうとしていること、そういうことを続けていったら将来外国に興味をもった子どもたちが、海外に出ていってふるさとの盆栽のよさを広めてくれるかもしれない。
時間がかかるのは重々わかっているけど、‘本物の盆栽’をここから広めていくっていうことに注力していきたい。
盆栽の形も、多様化し、苔玉や小さな花ものを中心とした盆栽、壁にかける盆栽、パフォーマンスを伴った盆栽など、エンターテインメント性があったり、現代のライフスタイルによく合致したりするものもある。
「そういうのもおもしろいし、盆栽の取っ掛かりとしてはいいと思うよ。僕も見ていて楽しいのもあるし。新しいことで盆栽に興味を持ってもらう人が増えるのはいいことだと思う」
平松さんが、急に厳しいまなざしになった。
「僕がやっているのは本物の盆栽、‘ゆるぎない正統派’、やと思っている」
盆栽は生き物、一期一会、その緊張感と、自然の景色を体現する静謐さ、変化していく危うさと確固たる普遍性、人工的であって自然な趣。
その本物の盆栽で勝負して、それを世界に広めたい。
「父を見ていたせいか、新しいこと、新しいビジネスモデルを構築し確立しつつ、地域貢献をしていきたいね」
平松春松園を訪れる外国人に慣れ親しんだ幼少年期、野球に明け暮れた10代、死に物狂いで勉強した浪人時代を経て、一通りの享楽を覚え、植物についてと英語を学んだ大学時代。
素直に飛び込んだ盆栽の道。逃げ出したくなりつつも、盆栽の仕事の意義を見出した盆栽の道に入った最初の10年。
自分の盆栽の技術を磨き、展示会や品評会に出された盆栽が賞を取ることに喜びを感じ、海外での活動に新鮮味を覚え、俯瞰で見えてきた自分のやるべきこと。
「盆栽は古くは奈良の正倉院に残される‘仮山’に基礎が見られ、鎌倉時代に日本独自のものとして確立されてから800年程の時を経て受け継がれてきた日本の誇る文化であり、芸術。国内での盆栽需要の落ち込みや、生産農家の減少、後継者不在など一筋縄ではいかない問題を抱えてはいるが、‘本物の盆栽’を守り抜いて、後世に伝え残していくのが僕の使命」